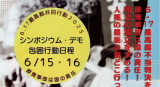【賛同】柏崎刈羽原発の再稼働の前提となる緊急時対応を了承しないでください
【賛同】柏崎刈羽原発の再稼働の前提となる緊急時対応を了承しないでください
緑の党は、「規制庁・規制委員会を監視する新潟の会」など3団体が、原子力規制委員会や新潟県知事に提出する「柏崎刈羽原発の再稼働の前提となる緊急時対応(避難計画)を了承しないでください—避難も屋内退避もできず、住民が置き去りに」に賛同しました。
内閣総理大臣(原子力防災会議議長) 石破 茂 様
原子力規制委員会委員長(原子力防災会議副議長) 山中 伸介 様
新潟県知事 花角 英世 様
柏崎刈羽原発の再稼働の前提となる緊急時対応を了承しないでください
-避難も屋内退避もできず、住民が置き去りに-
柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる地元同意の判断の要件一つが、実効性のある原子力防災計画・避難計画となっています。
現在、内閣府が設置した柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会において、柏崎刈羽原発立地・周辺の各自治体の計画や国の対応をとりまとめた「緊急時対応」の策定を進めており、地域原子力防災協議会が原災指針に沿っていることを確認し、原子力防災会議による了承を受けることになっています。しかし、その内容には多くの問題があり、実効性に欠くものと言わざるをえません。これでは万が一の事故の際、住民の安全は保障されません。
中でも、原発事故と地震、豪雪など、複合災害が発生したときの避難の問題は深刻です。原子力規制委員会の定めた原子力災害対策指針は、原発で深刻な事故が発生し、全面緊急事態となった際、PAZ(原発から半径5㎞圏内)の住民は即時避難、 UPZ(半径5-30km圏内)の住民は屋内退避ということになっています。しかし、能登半島地震では、多くの家屋が倒壊し、避難路も通行不能になり、多くの孤立集落が生じました。つまり、地震等の天災と原発事故との複合災害では、避難も屋内退避もできない状況となりえるのです。
大雪等の悪天候と重なった時に、道路が通行できなくなり、避難が困難になることも予想されます。柏崎刈羽地域の緊急時対応(案)では、暴風雨や大雪の際には、自宅などで屋内退避となっています。しかし5km圏内では屋内退避を実施しても、被ばく線量がIAEAの判断基準(実効線量100mSv)を上回ります (注)。すなわち「重篤な確定的影響を回避する」という原子力災害対策指針の要求を満たすことができません。
放射線防護対策施設が設けられていますが、避難が困難な要支援者を対象としているため収容人数には限りがあります。たとえば原発から北東2kmの高浜コミュニティセンター(宮川地区)は収容可能人数が65人ですが、原発至近の大湊地区と合わせた地区住民210人を収容することはできません。さらに、能登半島地震の際は、多くの放射線防護対策施設が損傷や異常が生じて使えない状態になりました。
このほかにも、問題は多く、原子力災害の際に住民を被ばくから守るものとはなっていません。
以上の理由から、私たちは柏崎刈羽原発の緊急時対応計画を了承しないように求めます。
呼びかけ団体:原子力規制を監視する市民の会
国際環境NGO FoE Japan
規制庁・規制委員会を監視する新潟の会
注)原子力規制委員会の「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」の資料として示されているJAEAのシミュレーションによれば、非常に甘い想定(セシウム137が0.45テラベクレル)あっても、PAZの一部で実効線量100mSvを超えます。また、2014年のシミュレーション(セシウム137が100テラベクレル放出、福島原発事故の100分の1程度の規模)ではPAZの一部で350mSvを超える結果が示されています。
https://foejapan.org/issue/20250513/23967
※現状の避難計画では、例えばバスでの避難一つとっても、こんなに実現不可能と中山均さん(新潟市議・共同代表)の報告。⇨https://x.gd/5p43B
※署名は5/26(月)の政府との意見交換会の冒頭で提出