【インタビュー】清末 愛砂さんに聞く「イスラエルのガザ攻撃から、国際社会の構造的矛盾を探る」
イスラエルのガザ攻撃から、国際社会の構造的矛盾を探る
ハマスらがイスラエルへの奇襲攻撃を開始した2023年10月7日以降、イスラエルは「自衛」の名のもとにガザを猛攻。民族浄化と言うべき惨状が続いている。その中にあって憲法前文の「平和的生存権」を基軸にパレスチナ問題に取り組む清末 愛砂氏は、国際社会の構造的矛盾に言及。その上で、「停戦後」を含めたパレスチナ和平の在るべき姿について冷静に分析し、日本の市民が取り組むべき課題やスタンスについて、憲法学者ならではの問いかけをしてくれた。
室蘭工業大学大学院教授
RAWA(アフガニスタン女性革命協会)と連帯する会 共同代表

清末 愛砂 さん
1972年生まれ。23年前からパレスチナ問題に関わり、度々現地に赴く。
憲法前文にある「平和的生存権」を、パレスチナを含めて全世界で実現するための活動に注力している。
(インタビュアー)
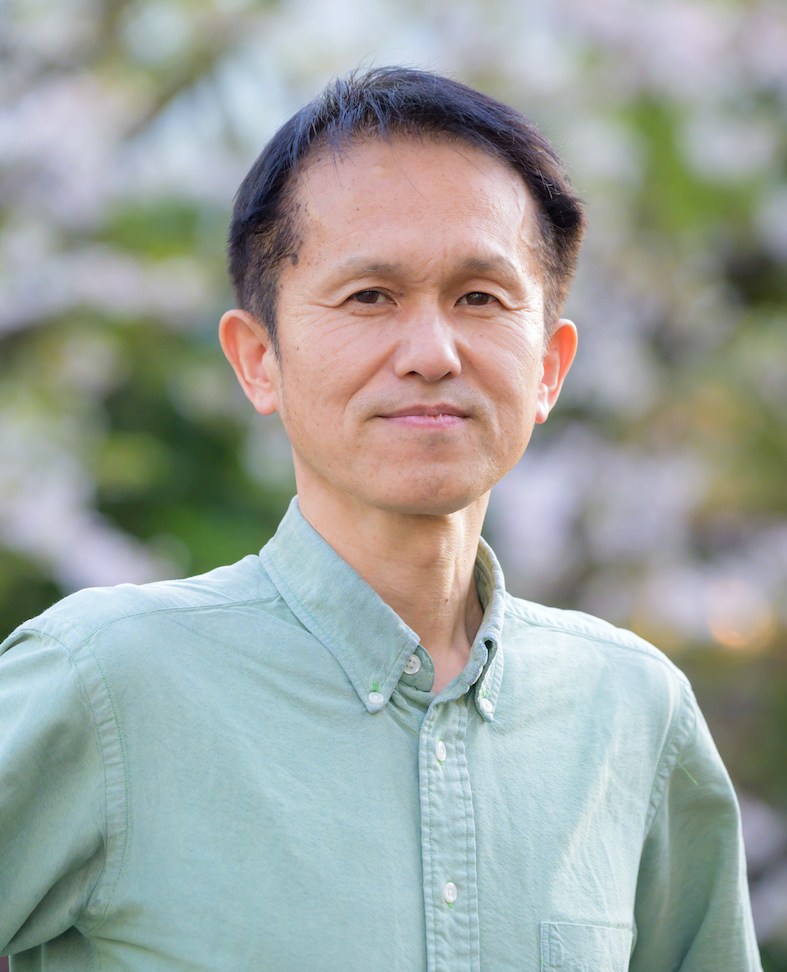
杉原 浩司
緑の党グリーンズジャパン 東京都本部共同代表
1965年生まれ。緑の党で脱原発・社会運動担当も務める。また、市民団体「武器取引反対ネットワーク」代表として、武器輸出に反対する活動にも注力している。
長期化・甚大化するイスラエルのガザ攻撃 その根底にある国際社会の構造的課題
―― ハマスを中心とするパレスチナ武装勢力がイスラエルへの奇襲攻撃を開始した2023年10月7日以降、「自衛」の名のもとにイスラエルによる攻撃は激甚化しており、民族浄化と言うべき惨状が続いています。憲法学者として23年前からパレスチナの人々に寄り添い、ガザをはじめとする現地に幾度も訪れている清末さんは、いまの状況をどのように分析されていますか?
清末 去年の10月7日に起こったハマスなどによる「反撃的越境攻撃」は、実は突如として始まったわけではなく、そこに至るまでの伏線があったと考えています。まず、明らかに国際法違反であるイスラエルによるパレスチナ自治区の封鎖と占領による抑圧が長年にわたって続いていました。とりわけガザに対しては、パレスチナ人たちの生活を追い込み、首を絞めるような強い締め付けが猖獗(しょうけつ=悪い物事が猛威をふるうこと)を極めていたことを忘れてはなりません。
このような「終りがない支配」が続いていた背景には、国際社会が打開策を見い出せないという構造的な問題があります。今回のハマスなどによる越境攻撃は、その延長線上にあると考えるのが妥当です。
―― 今回のハマスなどによる攻撃は、イスラエルが過酷な支配を続けてきた中での「結果」に過ぎないというわけですね。
清末 その通りです。それがどのような結果になるかということを、私もそうですが、パレスチナ問題に関わってきた人のほとんどが、当初から予想できていました。「イスラエルがこれまで以上に大規模な攻撃に打って出て、比較にならないレベルの犠牲者が出るであろう」ということです。残念ながら、実際にその通りになっています。
さらに私たちが懸念していたのは、被害の側面のみならず、イスラエルが「自衛」という名のもとに、これまで同様に正当化するであろうということ。ここでもアメリカを中心とする欧米諸国がイスラエルの支持を表明するなど、イスラエルの思惑通りの国際世論が形成されています。
確かにアメリカはイスラエルの長年にわたる同盟国であり、軍事支援をしてきた関係ですから、当然といえば当然といえます。同時に国際社会のレジームが「民主主義 VS 権威主義」へと向かっていることが、そこに拍車を掛けています。つまり、「善と悪」、「我々と他者」といった二極化したロジックに立脚して、パレスチナ人を「他者化」してきたわけです。このことは特にドイツなどにおいて顕著ですが、日本のスタンスも基本的には変わりません。
つまり、国際社会のレジームが、イスラエルが自らを正当化できる強力なバックグラウンドになってしまっているのです。このような構造こそが、さらにパレスチナ人を側面から追い込み、虐殺の拡大を招いているといっても過言ではありません。
―― ロシアのウクライナ侵攻に続いて起こった今回の事態には多くの人たちが衝撃を受けていますが、パレスチナ問題に関わってきた方々からすると、予想通りになってしまっているということですね。
清末 21世紀にもなって国際社会が止めることができない事態になってしまっていることは、誠に遺憾です。しかも私は、ジェノサイドへの恐れを明確に危惧していました。初期の段階から破壊の規模が尋常ではなかったからです。ジェノサイドとは、「人種」や「部族」を意味するギリシャ語と「殺害」を表すラテン語を組み合わせた言葉で、日本語では「集団殺戮」などと訳されていますが、実際には1948年に「ジェノサイド罪の防止と処罰に関する条約」(ジェノサイド条約)が国連総会で採択されており、その第2条では「国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の全部または一部を集団それ自体として破壊する意図をもって行われる次のいずれかの行為」と定義されています。法学者である私の危惧は、その条約を踏まえたもので、非常に重い意味を持っているのですが、今回はその可能性を強く疑っていました。悲しいことに、これに関しても私の危惧が現実になりそうな方向で事態が動いているのが、現状であると考えています。
―― 人類は2つの世界大戦を経て、その教訓からさまざまな国際人道法や国際刑事裁判所、国際司法裁判所などを設けることで戦争を止めたり、あるいは責任を問うような仕組みを築いてきたはずです。それでも止められないというのは何故なのでしょうか?
清末 戦争を止めることができないという理由は1つではなく、いくつもの機能不全があるからに他なりません。その象徴として多くの人たちが問題を指摘しているのが、国連の主要機関の1つである国際連合安全保障理事会(安保理)の位置付けです。安保理の決議というのは、勧告は別にして法的拘束力を持っています。つまり、イスラエルを含めて国連加盟国はその決議に従わなければならないわけです。ところが、停戦に向けた安保理決議はなかなか出ない。その理由は明確で、常任理事国(中国・フランス・ロシア・英国・米国)の中に「拒否権」を発動する国があるからです。今回の問題でも、アメリカのみならず、イギリスなどはイスラエル擁護の立場を表明しています。安保理の決定は、常任理事国の反対が1カ国でもあった場合には成立しないため、まったく前に進まないというのが現状です。
―― 安保理の機能不全はいまに始まったことではありませんが、他に打つ手はないのでしょうか?
清末 安保理決議が通せずにどうにも動かしようがない状況が続く中で、次なる一手を打ったのが南アフリカです。昨年の12月29日、南アフリカは「ジェノサイド条約」に基づいてイスラエルを国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、暫定措置を要請しました。これはイスラエルがジェノサイド条約違反に該当するかを直ちに認定させることを目的としていたわけではありません。ジェノサイドの認定には多くの時間を要するわけで、南アフリカはICJに暫定措置命令を出させることで、現在進行中の状況を改善しようと考えたのです。この要請を受けてICJは今年の1月26日、イスラエルに対して、ガザ地区のパレスチナ人との関係においてジェノサイドおよびその扇動を防ぐための措置をとること、緊急に必要とされる基本的サービスおよび人道支援を供給することを可能とする措置をとることなどを命じました。
この暫定措置命令には「停戦」の内容が盛り込まれていなかったので、パレスチナ側にとっては多々不満はあったと思いますが、それでも思った以上に早く出ましたし、ICJがジェノサイドの蓋然性があるという前提のもとにかなり踏み込んだ暫定措置命令を出したことについては評価しています。ただし、これは法的拘束力を持っているものの、イスラエルが履行しない場合に、履行させる手段がない仕組みであることも事実です。南アフリカの提訴は革新的な第一歩を踏み出したとは思いますが、同時に限界も抱えているわけです。
―― 先の安保理を含めて、仕組みはあっても履行させるには至らないという現状があるわけですね。
清末 本来ならば、そこに最も基本的な手段である外交が一石を投じなくてはいけませんでした。私たちが報道から知ることはほんの一部にすぎないので表立っては出てきませんが、実際のところ、アメリカにしても水面下では外交努力によってイスラエルに圧力をかけているに違いありません。イスラエルの言動に対しては、バイデン大統領ですら呆れているはずです。それでも、イスラエルを止めることはできていません。アメリカですら外交を通してイスラエルを止められないのであればと、多くの国も諦めてしまっているようにも思えます。
なぜ、そうなってしまうかというと、そこには「法の解釈」の問題がクローズアップされてきます。とりわけ今回の一件に限らず、「自衛権」という問題は拡大解釈ができます。多くの大国が「イスラエルの自衛権行使を認める」というスタンスを表明しているのも、そこに拡大した解釈がなされているからに他なりません。当然、そこには日本も含まれます。
しかし、法の専門家として言わせていただくならば、「ガザ」、もしくは「ハマス等の武装勢力(ハマスだけではない)」に対して自衛権を行使することができるかというと、「否(できない)」と言わざるを得ません。何故ならば、自衛権の行使というのは基本的に「国対国」を前提としているからです。パレスチナは国家であるわけではありません。非国家主体に対して、しかも占領している側であるイスラエルが、自衛権の名のもとで武力を行使することを認めてしまうと、より恐ろしい事態を招くのは明白です。
このことは授業中の学校がミサイルで砲撃されるなど、現地の惨状を目の当たりにした自身の体験から身に沁みて感じていることでもあります。それをあろうことか、先進国といわれる国々が認めてしまっているのです。
―― 「自衛権」に関する国際法上の解釈との矛盾はないのでしょうか?
清末 もちろん、国際法上の解釈は異なっています。人によって表現の仕方が違いますが、イスラエルがヨルダン川西岸地区に建設している隔離壁、いわゆるセパレーションウォールに対して、国際司法裁判所は以前、自衛権の行使を認めないという判断を下しています。国連の専門家もまた、「自衛権」に関して私と同様の解釈を示しているのです。こういった専門家の判断をすべて無視して、曲解・歪曲した「自衛権」の解釈が横行していること自体がおかしな話で、先の安保理・外交・法的拘束力の履行手段などといった問題が全部詰まったところで、国際社会を含めて誰もがイスラエルを止めることができない、つじつまが合わない撞着(どうちゃく=つきあたる・ぶつかる)した状況に陥っているのです。
――それでもイスラエルは、自らの正当性を主張し続けられているのは何故でしょうか?
清末 反駁(はんばく=主張や批判に対して論じ返すこと)するのはどこの国でも当たり前かもしれませんが、イスラエルが他国による批判に対峙する際の主張と方法は特に狡猾です。ICJが暫定措置命令を出した際にも、それが顕著でした。法的には太刀打ちができないので、イスラエルは政治的手段を使ってプレッシャーをかけて、やり返してきたのです。例えば、今回は「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)」の職員が、昨年の10月7日の越境攻撃に関わった疑いがある」と主張し、アメリカなどにプレッシャーをかけて、UNRWAに対する支援を止めさせようとしました。当然ながらイスラエルは、そのことによってパレスチナ人たちをさらに追い込むことができることを確信しています。一言でいえば、「飢餓」により壊滅的な打撃を与えるのです。ガザを封鎖し続けてきたのもそういった側面を持っており、これまで以上のレベルでそれを強化・拡充しようとする魂胆が分かります。もちろん、「飢餓」を「武器」にするのは国際法違反ですが、それがどれだけ人々を苦しめることができるかということを、彼らは重々承知の上で政治的プレッシャーをかけてパレスチナ側の息の根を止めようとしているのです。
これに対して、日本を含めてこのようなイスラエルの主張に同調する国があることが問題をより深刻にしています。日本はようやくUNRWAへの支援を再開し、つい先日には国連の報告書も発表されました。ところがその報告書には、イスラエルの関与の証拠がまったく示されていませんでした。このことが何を意味するかというと、政治的にプレッシャーを与えれば、さまざまな方向から相手を追い込むことができるということを、暗にイスラエルに教えているようなものです。

日本政府の対応は「未必の故意」
日本の市民にとっても対岸の火事ではない
―― これまで日本は直接、イスラエルを支援するというスタンスは抑えてきたといわれていますが、今回はUNRWAの件を含めて、欧米寄りにシフトしてきているように見えます。日本政府の対応については、どのように捉えていらっしゃいますか?
清末 昨年10月7日にハマスによる越境攻撃が始まった初期の段階では、日本政府は従来通り、少し距離を置いたスタンスを保っていたように思います。少なくとも岸田首相は、「双方に自制を求める」という立場でした。経済安全保障の観点からも、「エスカレートして欲しくない」という思惑が先立っていたのだと想像できます。
ところが、昨年の11月3日~5日の日程で上川陽子外相がイスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダンを訪問し、それぞれの外相らと会談を行った頃から様相が変わってきます。改めてハマスなどによる攻撃を断固として非難する旨を述べ、「イスラエル国民との連帯の意」を表明するとともに、日本の立場として「二国家解決」を普遍とする主旨を述べたのです。このことは先に述べた伝統的な国際法上の解釈と矛盾します。個人的には公文書管理担当大臣を務めていた頃の上川氏の言動には部分的には評価すべきところもあったので、大変、残念に思いました。多分、上川氏だけの見解ではなく、日本政府としてアメリカに追随したスタンスにシフトしていったに違いありません。
そのことを象徴しているのが、一時的ではありましたがUNRWAへの資金供与の停止措置です。直接的な武力支援にはつながらない間接的な手段であったとしても、その先に何が起こり得るかということを、日本政府が分からないはずがありません。「飢餓を武力化する」という観点において、まさしくイスラエルに加担したことを意味します。一歩譲って、パレスチナ人を苦しめたいという意図がなかったとしても、それはそれで日本政府が想像力を持たない政府であることを露呈しているということに他なりません。
このような状況を、法律の世界では「未必の故意」といいます。つまり、「結果を予想できるのに、実際にそうなってもかまわないと思って行為に移すこと」を意味する「故意の一種」です。結果的にガザの人たちの生命線を切ることにつながるのは明白なだけに、日本政府の対応には人道的な視点が欠けていたと思います。
―― 清末さんは憲法学者として、日本国憲法前文に明記されている「平和的生存権」を基軸にパレスチナ問題に取り組まれていますが、その観点からの問題を指摘してください。
清末 日本国憲法の前文には、国民主権・代表民主制・基本的人権の尊重・平和主義・国際協調主義といった憲法全体のエッセンスが凝縮されており、これらの理念が憲法全文の解釈基準となっています。その中で憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」として、全世界の国民の平和的生存権を規定しています。憲法とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める最高法規です。国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)を規定し、為政者の独裁や暴走を許さないために国民が定めた決まりです。つまり、第一義的に憲法を守るべきは為政者であり、憲法前文の理念に沿って国が動いていかなくてはならないのです。
その意味において日本政府が「未必の故意」ともいうべき対応をしたことは、憲法の精神に即していないと言わざるを得ません。逆にいえば、すべての日本国民が今回の問題を通じて、「全世界の国民に平和的生存権がある」ということを確認し、問うていく義務があるということ。日本国憲法を有する我々にとって、ガザは決して対岸の火事ではないのです。
―― 間接的であっても外務省がイスラエルの思惑を汲み入れたこともそうですが、防衛省は安保3文書(国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画)に基づく軍拡計画の一環として、殺人ドローンとも呼ばれるイスラエル製の無人攻撃機(攻撃型ドローン)を導入しようとしています。このことはジェノサイドが指摘されるイスラエルの軍需産業に加担することになりませんか?
清末 ここで指摘すべきは、想像力と倫理感の欠如です。日本政府はあくまでも自国の防衛の問題だという大義名分に基づいて、ガザと結び付けていないとする主張や言い訳を展開するでしょう。しかし、このレトリックには、イスラエルを利することで、結果として国際法違反の攻撃の容認につながる可能性をイメージする想像力もなければ、パレスチナ人の平和的生存権を守るという倫理感もありません。要は、自分たちはイスラエルに対して直接的に武器を供与するわけじゃないから問題ないというスタンスです。だから、倫理観というところに辿り着かないのだと思います。
―― つい最近、国連の人権理事会が、イスラエルへの武器の売却停止を求める決議を賛成多数で採択しましたが、アメリカなどが反対し、日本は投票を棄権しました。やはり、アメリカに忖度しているのでしょうか?
清末 忖度の対象は、決してアメリカだけではありません。むしろ、イスラエルとの現在の関係を保つことによって日本の防衛産業を支えるという発想に起因しているように思います。その伏線ともいえるのが、岸田政権が矢継ぎ早に防衛力の抜本的強化を掲げた施策を立法化させていることです。昨年12月に改定した安全保障関連3文書では、「防衛産業は国防を担うパートナーというべき重要な存在」と明記。なかでも昨年6月に成立した「防衛産業支援法」は、自衛隊の任務に不可欠な武器を製造する企業を対象に国が積極的な支援を行うというもので、日本の再軍備化に拍車を掛けることになりかねないと考えています。無人攻撃機の導入も、その流れの中で起こっている事象の1つに他なりません。
先程、皮肉を交えて「自国防衛」のレトリックに言及しましたが、「防衛産業支援法」は自民・公明の与党はもとより、立憲民主党などの一部野党を含めた賛成多数で可決・成立しています。この法律は日本の防衛路線を示すというよりは、むしろイスラエルのような軍事大国、もしくは軍需産業大国との関係を深めていくことにゴーサインを出す法律といっても過言ではありません。それはなぜかというと、今回のような国際法上の問題が起きた際にも、「防衛」の名のもとに、相手国の主張も自国の対応も正当化できるようになるからです。その法的根拠になり得る、というのが「防衛産業支援法」における最大の問題です。法学者として、非常に苛立ちを感じています。
加害性に目を向け始めた人たちに期待
1人ひとりの声を「点」から「面」へ
―― あまりにも残忍な殺戮が続く中で、日本においても各地で声をあげる人たちが増えています。市民の動きについては、どのように感じていらっしゃいますか?
清末 2015年の安保法制の際にも若者を含めて日本中で反対の声が盛り上がりましたよね。一方、経済安保に関しては、盛り上がりに欠けているように感じています。とはいえ、人々は常に無関心でいるわけではなくて、「これはおかしい」という局面では、声をあげる人が増えていくという実感は、今回の問題でも確認できています。これまで疑問を感じていなかった人たちが、声をあげ始めていることも事実です。同時に日本社会における様々な矛盾、構造的な暴力、例えばLGBTQ+や差別、ハラスメントの問題などについて意識を持って抗ってきた人たちが、イシューを超えてガザへの攻撃に真っ向から声をあげていることに、私は深く共感しています。なぜなら、自分たちがこのガザ攻撃にどう関わっているかということを、真摯に考えているからです。いうなれば、「自分たちも加害者ではないか」という観点に立脚したつながり方。それを運動の中で示していることが非常に強く伝わってきます。
それは、彼ら彼女たちが、構造的な矛盾と対峙しているからに他なりません。その意味では、従来の平和運動とは一線を画しているような気がしています。確かにスローガンとして、「戦争を止めろ」、「停戦しろ」といった声をあげることは必要不可欠ではありますが、それが「構造」という自分たちの足元から発せられているかというと、そうとは言い切れません。なぜ、このような虐殺が起きているのか。なぜ、悲惨な攻撃が繰り広げられているのか。それを引き起こしている構造を、別のイシューの観点を含めて俯瞰し、丁寧に見ようとする若者たちがいることが、私を勇気付け、希望を抱かせてくれています。
―― 病院で300名を超える遺体が発見されたり、ガザ最南部のラファへの侵攻が開始されるなど、民間人への被害は拡大の一途を辿っています。ますます逼迫する状況の中で、国際社会あるいは市民に求められていることは何でしょうか?
清末 まずは、声を出すレベルを増幅させなければならない、そして諦めずに発信し続けるということです。イスラエルはガザを徹底的に壊滅したいのだから、何を言っても止められないとなってしまうと、彼らにとって優位な土壌が形成されてしまうからです。その意味でイスラエルにやりやすい状況を与えないためにも声を出し続けなければならないし、さらには抗議の声を拡げることが重要になってきます。
そういう意味ではSNSなどを通じて「こういう声がある」ということを共有していくこともその1つ。いろいろなところでさまざまな人が声を出しているということを、告知・認知・周知させていくことになるからです。
例えばアメリカでも、ニューヨーク大学やコロンビア大学をはじめとする全米の大学において学生たちのイスラエルへの抗議行動や大学の加担に反対する行動が激化していて、警察が介入する事態となっており、この映像がSNSなどを通じて全世界に流れています。そこには警察から弾圧を受けようとしている学生たちを前線で守ろうとする教職員の姿も散見され、かつてのベトナム戦争時代の光景を想起させます。大国であり、親イスラエルのアメリカだからということもありますが、少なくともそういう個々の声や活動が全世界にインパクトを与えていることは確かです。
もちろん、日本でも全国各地で抗議活動が繰り広げられています。このような各地の抗議活動がSNSで拡散されることで「点」から「面」になっていく……。SNSは、そういうツールになり得ると考えています。そして、日本をはじめ、各国で築かれた「面」と「面」が世界中でつながっていけば、声はより立体的になり、力を持った人たちが市民を「黙らせることができない」状況が生まれていくはずです。SNSには気を付けなければならない点も多々ありますが、実はそういった世界レベルの機運を築いていける時代になりつつあると思っています。
―― 日本政府に対しては、どのようなスタンスで臨むべきなのでしょうか?
清末 政府への呼びかけや交渉に際しては、とりわけ法的な観点からどれだけ問題があるのかということを共有して、指摘していくことが大切です。特に憲法は為政者を縛り、暴走を許さないための仕組みでもあるわけですから、被害状況などの定量的な根拠を踏まえて憲法の理念に反していることを論理的に訴えていくことが鍵を握るでしょう。要は政府が遵守しなければならないことを突き付けていくということです。
イスラエルの問題は、多くの国民が自国を「軍事に依拠している国」であるという自覚を持っていないこと。そこは日本が学ぶべき重要なポイントで、「防衛」の名のもとで自覚がないまま軍事化していってしまえば、日本もイスラエルのようになり得るという恐ろしさを内包しています。
「法」に基づく公平性をスタンダードに
「停戦」以上に大切な停戦後の在り様
―― ウクライナの問題との違いは、欧米諸国や日本をはじめとする「民主主義国家」といわれる国々が、イスラエルに対してダブルスタンダードといえる姿勢を見せていることです。ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ虐殺の根底にある普遍的な問題を、私たちはどう考えるべきだとお考えですか?
清末 アメリカはもちろんですが、イスラエルに対するドイツやイギリスの動きを見ていると、明らかに政治の論理の方が勝っているという気がしてなりません。法学者だからといわれるかもしれませんが、政治は重要ではあるものの、やはり公平性を担保する際には「法の支配」に基づいた考え方をスタンダードにして判断していくべきです。ロシアのウクライナ侵攻が始まってから、その重みを改めて実感しています。
もちろん、法の支配がリアリティの観点で多々問題があることも事実ですし、法の運用という観点においても、例えば男性を中心とするマジョリティがいいように使っていた歴史があったことも事実です。それでもやはり、国際法などの概念に基づいて公平性を担保できる方向が示されていけば、現状よりはるかにましになるに違いありません。
「国際法は無力だ」、「国際法だけでは助けられない」という人もいるでしょう。とはいえ、国際法がいまの状況を認めているわけではありません。イスラエルがパレスチナに対して実行している行為、実際にはガザだけではありませんが、これに対してICJをはじめとする各機関は少なくとも国際法の秩序に著しく反していると唱えています。にもかかわらず、イスラエルは国際法に抗い続け、アメリカをはじめドイツやイギリスもそれを支援しているのは、国際法の問題ではなく、国際政治がその実行力を歪めているからです。この状況を打破するためにも、世界中の市民に「法の支配」の効力に目を向けて欲しいと考えています。
―― 法の実行力を高めていくためには、どのような視点が必要でしょうか?
清末 その第1歩は、レイシズムや植民地支配の問題性に対して、真摯に向き合っていくことだと思います。イスラエルはまさにパレスチナを植民地支配しているわけで、21世紀のいまなお、それを大国が支持しているというのは有り得ない話です。
実はここにも「法」の問題が関係しています。いわゆるイスラムフォビア(イスラム恐怖症)ともいえる非常に差別的な発想に立脚して、適切な法の適用がなされていないのです。まさしく「彼らは我々とは違う」というレイシズムのロジックのもとに、パレスチナ人たちは「法の支配」の範疇外に置かれているのです。まずはこういった側面を注視していくことが、特にパレスチナ問題においては肝要です。
―― これまでのパレスチナ人虐殺に反対する取り組みは、「停戦」になると動きが収まることの繰り返しだったように思います。特に被害が甚大で長期化している今回は、「停戦後」の賠償や責任追及、被害者へのケアを含めてより本質的な方向を模索していく必要があると考えますが、そこでのポイントはどこにあるのでしょうか?
清末 差し当たっては、兎にも角にも「停戦」を求めていかなければならないのは当然ですが、停戦後がより大事であることは間違いありません。停戦しても、「封鎖」が続いていたら、まったく意味をなさなくなってしまうからです。それだけに「封鎖」を解除するということが非常に大きなポイントとなります。ただし、それだけでは十分ではありません。根本的にはイスラエルのパレスチナ占領を終結させるということをゴールに据えるべきだと考えます。
その解決方法について尋ねられることも少なくないのですが、最終的には当事者であるパレスチナ人たちを主体に決めていく必要があります。よく言われているのが「二国家解決」ですが、実はこれにも複数のバージョンが想定され、パレスチナ人の中にもこれを求めている人たちが少なからずいることは事実です。であるならば、少なくともそれを支持していくべきであることも確かですが、私は問題のそもそもの根源は「オスロ合意」にあると考えています。ヨルダン川西岸地区の実情が、まさしく「オスロ合意」故のアパルトヘイトに他ならないからです。
オスロ合意は1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)との間で合意された一連の協定で、故郷と家を失った多くのパレスチナ人が流入したヨルダン川西岸地区が、ガザ地区とともに「パレスチナ自治区」になったわけですが、実質的には生活圏を分断する巨大な隔離壁が築かれ、イスラエルの軍事支配下で常に厳しく監視されています。それだけに、「オスロ合意」に挑戦する国際社会がなかったら、何の解決にも行きつかないと思うわけです。
例えば、ハマスなどが越境攻撃を実行したのも、ある意味で「オスロ合意」以降の体制に対するアンチテーゼだといわれています。「オスロ合意」がイスラエルを利するロジックとして利用され、それに基づきパレスチナ人たちは抑圧され、従属せざるを得ない関係が築かれてきたからに他なりません。実際にはパレスチナ自治区の中でも「オスロ合意」に対する見解は一様ではないようですが、再考すべきタイミングであることは確かです。


